11月10日(土)の午後2時からレゾナンスCafe Vol.027 「沖縄文学と出会う―目取真俊『希望』を糸口として」をおこないました。講話をしてくださった臼田夜半さんの沖縄での体験、そして目取真俊さんとの出会い、臼田さんの研究していた魂のあり方に関して、同じと感じるところ、沖縄独特と感じるところなどお聞かせいただきました。
内容はものすごく繊細なものなので、語っていただいたほぼ全文を掲載いたします。
目取真俊さんとの出会い―あるいは存在の全体性
私は沖縄文学を読んだことがありませんでした。知らなかったんです。二年前に沖縄に行き、高江に行きました。やんばるの森から米軍基地に入って阻止行動をするために行ったのですが、現場に着くだけでも大変なところでした。そこで座り込みなどをする訳ですけど、四人で行って、そのうち二人が女性で、長い時間はそこにはいられないというか、一日中いる覚悟が私たち全員にはなかったと思います。午前中で山を下りることになったのですけど、そのとき私たちのはるか前方の最前線に立っていたのが目取真俊さんでした。
彼は機動隊員の前でひとり毅然として立っていた。やんばるの森に入るとき、ハブもいますし、迷ったら出て来れないようなとこですから、バディを組んで、必ず二人一組で行動するようになっていました。わたしとバディを組んだのは76歳の方で、沖縄の南側出身の方で、軽四輪に三日分のおにぎりを作ってクーラーに入れてもってくる。そのときは野宿ですから近くの川をお風呂代わりにしていました。三日経っておにぎりがなくなったらまた家に帰って戻ってくる。その方に「先頭にいるのは目取真さんだよ」と言われ、実は名前も知らなかったんです。どういう字を書くのかすら想像できない。「芥川賞作家だよ」と言われても「いやぁ、知りません」というそれがすごくショックでした。実はなんにも知らないで来ている。自分自身にとってショックでしたね。
私たちが山を下りるときに、山を下りる私たちに向けて目取真さんが深々と頭を下げたんですね。その瞬間に、ああもう裏切れないなと思うんですよね。帰ってから、あわてて目取真さんの本を取り寄せて読み始めました。それは必ずしも私だけではないと思うんです。加藤周一という人が『日本文学史序説』という本を書いています。1975年くらいの出版で、万葉集から始まり、芥川を通って、小林秀雄で終わっているんです。そこには沖縄の「お」の字もなければ、アイヌの「あ」の字もない。加藤周一の場合は万葉集から始まっていますから梁塵秘抄とかがでてきます。しかし沖縄の場合は「おもろさうし」という、時代は下りますけど膨大な歌があって、日本の短歌にあたるものが琉歌としてあって、でもそれはまったく無視されている。日本文学史の中で。でも何も知らないということを通して、実は私もそのようなことに加担している一人だったということがすごくショックでした。それから目取真さんの文学と言うか、目取真さんとの出会いがそうだったので、たぶん私は目取真さんという作家の存在に興味を持ったんだと思うんです。彼はやんばるの奥深い森に入り、いまは辺野古で海上抗議行動をやっています。辺見庸との対談の中で、カヌーを漕ぎ過ぎて手の指紋がなくなったということをおっしゃっていますが、彼は芥川賞作家なんですね。もう十何年か長編小説は書いてないんだと思います。彼は文学と政治はまったく別のものだとおっしゃっていますが、でも今、カヌーを漕ぐことがまぎれもなく、目取真さんの全存在性の一部を表現するものだろうと私はそう思っています。今日お話しするのは目取真さんの文学という側面を通して、作家でありながらカヌーを漕いで戦う存在とはいったい何なのかということを一緒に考えていただければなぁと思うんです。目取真俊という沖縄文学者のもつ存在の全体性。文学作品による表現という部分に限定しない表現の全人格性といいますか。それはどこから来ているのか、と言い換えてもいいかもしれません。
精神構造を鍛える
日本の文学者の中でそういう人は稀有なんです。それは戦前も同じで、実際に体を張って戦争に反対した文学者ってほとんどいないですね。さっきの小林秀雄にしても戦争に加担している。戦争賛美の文章を書いてますし、それでも戦後一流の批評家と言う名をもって生き続けられた、ということなんですね。何が違うのか、本土の文学者と沖縄の文学者。何が違うのかということを、目取真さんについていえば、目取真さんの書かれている作品を通じながらそのことを考えてみたいというのが、今日の私が話したいと思った意図です。
レジメにあるのが目取真さんの主要な作品の引用です。その一番初めにありますけど、これはある対談の中での言葉です。
「ある重み・苦痛を伴うような問題に、ぼくらはどこまで耐えられるのか。重く、つらい体験を追体験し、考えていくだけの精神構造をもっているか…。」
新城育夫『沖縄文学という企て』261p/雑誌「キョラ」6号「溶解する記憶と記憶の境界」(奄美研究会)
沖縄はご承知のように地上戦を経験した唯一の戦場ですね。かつそのなかで集団自決という名の集団死を強制されて、親が子を殺し、子が兄弟を自らの手にかけざるを得ないという、そういう記憶。沖縄文学はこの戦争の記憶抜きには存在してないし、目取真さんの文学も明確にそこを起点に語られているものです。この重くつらい体験を正面から考えていける精神構造を自分は持っているのかという自問。この作家の精神構造を造り上げている肉体と魂とはいったいどのようなものなんだろうというのが、私の興味をもっている点です。
きつい批判
今日のお話のタイトルに「目取真俊『希望』を糸口として」としましたけど、目取真文学は実は本土ではあまり読まれてないだろうなと思いましてね。私自身がそうだったからということもあるんですが。この『希望』(目取真俊短編小説選集3『面影と連れて(うむかじとぅちりてぃ)』内 『コザ/街物語』よりの一篇)というのは400字詰め原稿用紙で5枚くらい2000字くらいのものですから、最初にそれを前もって読んでいただいて、共通のテキストがないと話しにくいからと思っていたんですけど、他の作品と同じような扱いで背景と要約を読み進めようと思います。というのは、目取真さんの作品ほど叩かれている作品はないと思うんです。ネットをみればわかるんですけど、むちゃくちゃ叩かれている人なんですね。特に『希望』はそうなんです。2000字くらいの短い文章ですが、完成度の高い甲虫みたいにギュッとしまった文章なんですけど、凄まじい批判を受けているんですね。どういう話かというと、1995年に、ご承知かと思いますが、12歳の女子小学生が米兵三人に強姦されるという事件があったんです。目取真さんの作品は繰り返しこの事件を巡って書かれています。その前には1955年かな、6歳の女の子が米兵に強姦されて殺されたという事件があるんですね。そしてつい2年前にも起きました。で、この『希望』というタイトルの小説はそれに対する県民弾劾集会が85,000人くらい集まって催されるんですね。それに参加していたたぶん18か19くらいの青年だと思うんですけど、その彼に「いくら人間が集まったって一人の子どもの命を守れなかったじゃないか」と作品の中で言わせているんです。それで小説の主人公は報復を決意する。目取真さんの扱う暴力は常に弱者の側の、しかも単独の暴力―単独の抵抗ですね。『希望』を読みましょう。
今オキナワに必要なのは、数千人のデモでもなければ、数万人の集会でもなく、一人のアメリカ人の幼児の死なのだ。(中略 以下…)奴らは従順で腑抜けな沖縄人がこういう手を使うとは、考えたこともなかったのだ。反戦だの反基地だの言ったところで、せいぜい集会を開き、お行儀のいいデモをやってお茶を濁すだけのおとなしい民族。…軍用地料だの補助金だの基地がひり落とす糞のような金に群がる蛆虫のような沖縄人。平和を愛する癒しの島。反吐が出る。(『希望』)
こうしてスーパーの駐車場に停められた車の中で眠っていた五歳くらいの白人の男の子を乗せたまま車を盗んで走らせ、森で絞め殺して車のトランクに入れるんですね。この話は小説の話であって、もちろん事実ではないですよ。米兵に強姦された女の子がいることは事実ですけど、それを恨んで男の子を殺すというのは小説の中の話です。小説の話に戻りますけど、その主人公は子どもの毛髪と抗議文を新聞社に送り、その足で弾劾集会があった公園に行ってガソリンをかぶって自殺します。黒こげになって燃えてしまう。それを走ってきた中学生のグループが蹴るという場面で終わります。
自ら火を放って黒こげになっている人を蹴っているというのは、たぶん(本土にいる)私たちのことなんです。そういう短い文章です。目取真さんは短編が多いんですね。この作品だけ読むとこれはまぎれもない暴力です。面白いのはこの作品を批評する評論家がまず何を言うかというと、「私はテロには反対である」とまず言うんですよね。非常に奇妙ですよね。たとえば殺人を扱った小説はたくさんあると思うんですが、そういう作品を評論するとき「私は殺人に反対である」、あるいは詐欺を扱う小説に対して「私は詐欺に反対である」ということを言うか? ここだけ切り出すとそういう話で終わってしまうなというのが、実はあったんですね。
『希望』は1999年の作品です。同じ米兵強姦事件を扱ったものに2004年の作品『虹の鳥』というのがあります。おそらくこれは目取真さんがこれまでに書いた長編の中では最後に当たるのではないかと思います。それ以降ずっとやんばるの森に、あるいは辺野古でカヌーを漕ぐことに集中しているように思うんですけど、これをちょっと『希望』との関係で見ていきたいなと思っています。目取真さんの『希望』に対してはいろんな批判があって、たとえば新城郁夫という評論家がこう言っているんですね。「男根主義的というほかない暴力待望的伝説」。あるいは他の評論家は「沖縄の実態をわからせるために少女を犠牲にした物語だ」。ジェンダーという考え方が流行ったときに彼はこういう批判のされ方をしたんです。男中心だ。沖縄の実態を明かすために少女を利用しただけじゃないか。これは実は集会の場で高校生の女の子がそういう発言をしたという事実もあるようです。それに対して目取真さんはその場では一切反論してないんですね。それに対する反論として書いたのが、おそらく2004年の『虹の鳥』という小説だと思うんです。
目取真さんの作品というのはですね、1999年にとんでもない数の作品を生み出しているのですが、ある時期の宮沢賢治みたいに非常に多作なんですね。目取真さんが作品を書いた時期というのはとても大事で、これは本土の作家にはあまりないことなんですが、沖縄が革新県政であったかなかったかということが非常に大きいんです。目取真さんの場合、革新県政であった間にわーっと溜め込んだものをそのあと保守政権のときにバッと出しているという、そういう出方をしているようで、目取真さんの作品の場合、その作品がどの知事のもとにあったかということがわりかし大事な意味を持っているというふうに思います。
この『虹の鳥』というのは、稲嶺恵一知事に変わった時期の、つまり保守に変わった時期の、沖縄国際大学に米軍のヘリコプターが墜落した年に出した小説なんです。
原初の生命力
簡単にあらすじをいうと、主人公はマユという女性で、高校のとき生徒会の副会長とか会長とかやっていた子なんですけど、あるときやくざのチンピラに集団で強姦されて、そのときの写真を撮られていて、それを元にゆすられて、ついにクスリ漬け、シンナー漬けになって娼婦に身を落としていくという、ほとんど拉致されたままの状態の少女が主人公なんですね。この主人公は死人のようにやせ衰えて、ほとんど食事もしない。毎日商売として強姦されているわけですから。『希望』のときには男性を主人公にしたものをここでは廃人のような女性を主人公にしている。これが目取真さんの反論、さきほどの批判に対する反論だと思うんです。ほとんど死にかかっているような女性がある日突然連続殺人を犯す。それがこの引用部分です。拉致した親分である男とそのすぐ下の手下の男と、自分をなぶりものにした女の子と、三人。最初に殺したのは、自分をいわば客として買った男なんですね。一番最後に、やんばるの森に逃亡するんですけど、その途中で米軍の子どもを殺すんです。そういうストーリーなんですけれどね。一人では食事も取れないような、17,8の女の子だと思います。それが以下の引用部分です。
今まで見たことのない眼差しだった。いつもぼんやりしたマユの眼差しが一変すると同時に、身のこなしまで変わってきた。裸身を隠しもしないでベッドから下りると、男のズボンからベルトを抜き、うずくまる背中に振り下ろした。(『虹の鳥』18P)
買った男に対して「まなざしが一変した」んです。次を読みます。
男を完全に屈服させているマユの動作は、それまでの日々からは想像もつかなかった。体はきびきびとして、細身の姿が少年のように見えた。(『虹の鳥』20P)
こういうふうになると。その後、比嘉という自分を貶めた暴力団のボスに、自分が嗅がされていたシンナーをぶっかけて火を放ってのどをナイフでかっ切るということをやるんですね。
マユが暴力を加えるとき、虹の鳥は生気を取り戻したように、肌から鮮やかに浮き上がってくる。(『虹の鳥』25P)
「虹の鳥」というのは背中に入れられた入れ墨のことですね、それが虹の鳥になっている。不死の鳥、フェニックスですよね。それがいわば生気を帯びたように蘇るという描写をしています。入れ墨というのはこれからあとで述べる目取真さんにとっての、身体論の、他の生物と同居するという最初の入口がたぶん入れ墨なんですね。入れ墨をしている人にはそういう感覚があるんじゃないかと思うんです。他の生命を自分のなかに刷り込むというんですかね。目取真さんは非常に特異な身体論を持っている人です。その最初がたぶんこの作品。時系列的には違うんですけど、そういう身体論を巡る最初のとっかかりはこの『虹の鳥』なんだなというふうに思います。
引用の四番目ですが、アメリカ人の少女を殺害したあと、車の後部座席でこう表現しています。
マユの目が開き、瞳の奥で何かが動いた。
「さっさと出せよ、クズ」。低く強い声だった。初めてマユの本当の声を聞いたような気がした。(『虹の鳥』219P)
廃人のような少女の目の色が突然変わり、声の雰囲気が変わって生命力そのものが動くように殺人を犯す。そういうとらえ方になっていると思うんです。さきほどの『希望』の少年も目取真さんのなかでは、暴力の根拠には、このマユのようなものがあるということを押さえて欲しいんですね。『希望』では政治的側面の匂いが強いですよね。米兵に対して報復するんだという。しかしこのマユのほうではイデオロギーとかそういうものは何にもないんですよね。しかも当人が自意識でやっているというよりも、マユの背中の入れ墨のような、原初的な生命力が発動したように殺人を犯す。
目取真さんにとって暴力とは何かというと、ひとつは、生命そのものが持っている本源的な尊厳だとか、そういうところに関わっていると目取真さんは見ているんではないか。
言っておきますが、目取真さんが沖縄でやっている運動は徹底した非暴力です。そこは勘違いして欲しくないんです。そのうえで暴力というのは、生命それ自身の発現ではないかというとらえ方をしている。ここは大事なことです。目取真さんが扱っている暴力をいろんな評論家が書くんですけど、フランツ・ファノンというアルジェリア解放闘争のときの、民族解放の際の暴力を扱った本が引き合いに出されることが多いんですけど、目取真さんはそれよりもずっと奥の方を見ている。命というのはその尊厳をかけてその力を発動することがある。私はキリスト教徒なんですけどね、旧約の神様ってそういうところがあるんですね。旧約の神様は決してお行儀が良くないんです。人を殺すときは殺す。そういうものを私は感じるんです。
この車を運転しているのはカツヤって男の子なんです。結局暴力に屈してその手下になっているんですね。実はマユはその男の子が好きになった瞬間があるんです。その男の子が比嘉にやられそうになって、暴力を発動していくんですね。カツヤという男の子は反撃できない。それに対してほとんど廃人のような女性がギリギリのところで反撃するというその姿。原初的な生命が持つ暴力性といいますかね、これはなんなのかな。
この『虹の鳥』のなかのマユという女の子の中の原初的な力が、もっとわかりやすく微笑ましい情景として描かれているのが『平和通りと呼ばれる街を歩いて』という小説です。
生命力の現れ出る瞬間
これは実はね、時代で言えば1986年なので最初の頃の作品なんです。主人公は認知症のおばあちゃんです。舞台はいまの天皇皇后が皇太子と皇太子妃だった頃、沖縄で献血全国大会というのがあって、この小説の主人公であるウタというおばあちゃんは戦争の中でやんばるの洞窟に逃げていて、そこで子どもを亡くし、旦那さんは戦争に取られて死んでいるという。だからあれだけ血を流させておいて何が献血だということを言うんですけどね。戦後ひとりで子どもを育てて行商をし、露天商をしながら生きてきた人を、皇太子夫妻が来るからと痴呆症などの人を予防拘禁するという。このおばあちゃんもそれをされかかっているんですけど、家族がさせなかったというのがあるんですね。カジュという孫は小学4年生だと思うんですけど、そのおばあちゃんの過去の苦しみを知っているものですから、皇太子が来たときにせめて唾くらいひっかけてやりたいと、沿道の最前列から飛び出そうとするんですね。すると突然ドンとからだを飛ばされて、何だと思うとウタだったんですね。
カジュのすべての神経が目と口に集中し、全身に鳥肌が立つ。カジュは思い切り一歩を踏み出した。次の瞬間、カジュは後ろから激しく突き飛ばされて路上に転がった。歯の折れる音が頭蓋に響き、金緑色の光が飛び交う中を猿のような黒い影が走る。カジュは死に物狂いで起き上がり、叫んだ。
「おばー」
それはウタだった。車のドアに体当たりし、二人の前のガラスを平手で音高く叩いている、白と銀の髪を振り乱した猿のような老女はウタだった。前後の車から屈強な男たちが飛び出し、ウタを引きはがすと、あっという間に皇太子夫婦の乗った車を取り囲んで身構えた。路上に投げ出され、帯がほどけて着物の前もはだけたウタの上に、サファリジャケットの男や、さっき公園でラジオを聴いていた浮浪者風の男が襲いかかる。両側から腕をとられながらも、ウタは老女とは思えない力で暴れまくる。(『平和通りと呼ばれる街を歩いて』 262p)
このときにウタは何をするかというと、皇太子夫妻の乗った車の窓に自分の糞を塗りたくるんですね。さきほどの『希望』の主人公は青年でしたが、『虹の鳥』では廃人同然の17,8の女の子でしたね。ここでは、いまでいう認知症のおばあさんが突然猿のように飛び出してきてそういう行動に出る。これを暴力と呼ぶかどうかはわかりませんけどね。抵抗ですね。ここには押しとどめられないものがあるんだと思うんです。私も深い病いを負った経験があって、何度か死の淵を歩んできているんですよね。面白いなぁと思うのは、生命力が本当に衰えて手も足も出ないんですね。そういうときに実はあらゆる自我が取っ払われるものだからファッと生命力そのものと呼ぶほかない力が現れ出る瞬間があるんです。本当に華やいで蛍の光のような光がフォワッと出る瞬間があるんです。さっきのマユという女の子も、このウタというおばあちゃんも、その体を突き動かしているのは、たぶんそういう生命力なんだと思うんです。目取真さんはそこに深い信頼があるんだと思うんです。そういう生命力というものがね、抵抗として表出される根拠にある原初的な生命の力を信じている。「ぬちどぅたから(命どぅ宝・「命こそ宝」という意味)」というんですかね。目取真さんのこの言葉の捕まえ方がここにあるんじゃないかなと私は思っています。
ウタは警察につかまって帰されるんですね。家でカジュのお父さんがウタを部屋に閉じ込めて、そこによくある緑色の留め金を差し込んで出られないようにした。それをカジュがはずそうとする場面が次の引用です。
ウタの部屋の戸は、掛け金がねじ切れ、ねじ釘が飛び出したまま斜めに傾いでいた。そっと手で押すと、ギィッという痛ましい声を挙げ、釘が落ちた。カジュはそれを拾い上げた。薄暗い家の中で、どこから漏れてくるのか一筋の光を受けて、真新しいねじ釘は怒り狂う動物の歯のように鋭く光っている。カジュは尖ったその先を自分の腕に突き刺し、縦に傷をつけた。熱くたぎった憎しみが体から吹き出す。カジュは力の限り戸を殴りつけると、不意に襲ってきた笑いの渦に体を震わせ、溢れる涙をはじきとばした。(『平和通りと呼ばれる街を歩いて』 264p)
ここは私が非常に好きな場面で、印象に残っています。四年生の男の子がそのおばあさんを閉じ込めていた鍵のかけ釘を取って自分を深く傷つける。さきほどの「重くつらい体験を受け止めるだけの精神構造を持っているか」というときに、目取真さんのなかではその痛みを頭で理解するのではなくて、自分のからだに刻み込むというのが記憶だと。その記憶というのは体に刻み込む。そしてそれを引き継ぐというのは小学生の子どもが自分を傷つけること。目取真さんは戦争の記憶をどこでどう引き継ぎ、どこで解放するのかということはもの凄く大きな沖縄の人たちの文学のテーマなのだと、それはここではこういう言い方をしている。肉体の痛みを呼び覚ますんですよね。頭で理解するのではなくて肉体の痛みを呼び覚ましてそれを記憶する。肉体の痛みとして記憶する。それ以外に痛みを引き継ぎ継承するということは目取真さんにとってない。
命の連なり
目取真さんがカヌーを漕いでいるのは辺野古なんですけど、お父さんは14歳のときに鉄血勤皇隊※1というのに取られている。日本兵からスパイじゃないかと殺されかかっているんですけど、実は辺野古の海岸からお父さんたちはイカダを作って安全な場所に脱出しようとしていたんですね。ところがイカダが壊れて打ち上げられてしまった。その同じ場所で息子の目取真俊さんはカヌーを漕いでいるんですね。自分の腕を傷つけるようにしてカヌーを漕いでいるということだと思うんです。この小説は最後にですね、カジュがおばあさんを、自分の子どもは山原(やんばる)で死んでいる、ご主人も行方不明になってたぶん死んでいる、そのおばあさんを起こしてバスに乗せて、やんばるに行くんですね。それが最後になって、これはバスの中の会話です。
「おばー、山原はまだかなー」
基地の緑は目に眩しく、カジュの体はうっすら汗ばむくらいだったが、ウタの手はいつまで経っても温かくならなかった。(『平和通りと呼ばれる街を歩いて』)
行くバスの中でおばあさんは息絶えているんです。こういう、つまり、いまの三つの話は、廃人だったり、おばあさんだったり、少年だったり、もっとも弱い人たちが、その抑えきれない原初的な生命力が発現するようにして抵抗行動は現れるという、そういう風に目取真さんは捉えている。そういう見え方をしているんじゃないかと思います。
もうひとつはね、最初の『希望』にあるんですけど、その青年にしてもマユにしても、あるいはウタの場合も、死を恐れてないんですね。なぜ死を恐れないんだろう。あとでいいますけど、『面影と連れて(うむかじとぅちりてぃ)』の主人公の「うち」という女性も、死を恐れていないです。死がすべての終わりだと思ってないんですね。これはあとで触れます。そういうものがやっぱりプラスされているんじゃないか。死への態度というのはその人の死生観を問われる訳ですよね。そのことがない限り、死を超えることはなかなかできない。目取真さん自身もそのことを巡っているんだなぁと思うんです。これはあとで言いますが、魂の捉え方についてすごく変化しているんです。面白いんですね。ものすごく正直な作家だなぁと思います。取り澄まして生きていけるような人ではないんですね。
異形の身体
いままで一応暴力ということを扱いしました。その暴力とは生命力の発現として目取真さんは押さえているのではないかということでしたが、その主体である目取真さんは肉体と霊魂をどう捉えているのかというふうに問題を少しずらしていきたいと思います。最初に目取真さんの身体論というか、身体のとらえ方を扱っていきたいと思います。非常に特異な人なんですよね。あの、カフカに朝起きたら昆虫になっていたみたいな作品がありますが、それは創作だと思いますけど、目取真さんを読んでいるとどうやら違うんですね。もっと実体験的というか、フィクションとして書いているんじゃないんだなということがあります。最初に扱うのが「魂込め」、まぶいぐみと読みます。ここでは精神が肉体に及ぼす影響、それによって肉体が異形化する、つまり私たちの身体・肉体と精神の間に境目がないんですね。肉体は精神によって異形化するという。その最初として、異形化する身体の現われとして、アーマン、オオヤドカリですね、それがひとりの男性に寄生するという話から始めます。
それは引用の一番「魂込め」というところなんですけど、要約しますとね、幸太郎という男の人、子どももいるんですけどね、アーマンというオオヤドカリが鼻の奥に巣食ってしまう。それをウタという、ウタという名前はよく出てくるんですよね、そのおばあさんが、ある種ユタなんだと思うんですけど、幸太郎は魂が落ちている状態だということで、魂を込めるというのが「魂込め」ということなんですね。それが最初の引用部分です。
乳飲み子の頃両親を失ったせいか、幸太郎は幼い頃からよく魂を落とす子供だった。… そのたんびにカマダーやウタが魂込めをしてやった。…
「又ん魂落としておるごとくあるむんな」
人騒がせな、と思いながらフミにいうと、うつむいて小さく首を横に振る。いったい何(ぬー)やが、と声を上げそうになったとき、ふと幸太郎の鼻から何か黒いものが突き出ているのに気づいた。最初は鼻毛かと思ったら急に引っ込んで、今度は唇の間から三センチほどはみ出し、頬や顎のあたりをちょんちょんと探るように動いている。驚いて見ていると今度は唇の間からマッチの頭のような目が突き出し、歯がむき出しになった。紫がかった灰色の爪が口をこじ開け、姿を現したのは大人のこぶしくらいありそうな大きな「アーマン」(オオヤドカリ)だった。(『魂込め』 11p)「幸太郎は魂落ちておるもん。やこと、自分の体を守ることもかなわん、アーマンに入られておるさ。やしが、心配(しわ)すな。魂の戻りねー、アーマンもすぐに出ていきよる。我(わ)んがすぐに魂込めすることよ。しばし、待っておれ」(『魂込め』 13p)
魂込めの儀式というのがあるんですね。その人の服を脱がせてお祈りして、もう一度服を着せなおすというのがもっとも単純なやり方らしいんですが、このときは何をやってもダメだったんです。最終的には幸太郎は死ぬんですが、ここでは異形化する身体の最初の形としは、他の生物が体に寄生するというとらえ方をこの作品の中でまずやったということを押さえておいて欲しいんです。本当の異形化というのは、次の『水滴』に端的に表れます。この『水滴』で彼は芥川賞を取っているんです。ぜひ読んで欲しいんですけど、資料を読んでみましょうかね。
徳正(とくしょう)の右足が突然腫れだしたのは、六月の半ば、空梅雨の暑い日差しを避けて、裏座敷の簡易ベッドで昼寝している時だった。五時を過ぎて少しは凌ぎやすくなっており、良い気持ちで寝ていたのだが、右足に熱っぽさを覚えて目が覚めた。見ると、膝から下が腿より太く寸胴に腫れている。あわてて起きようとしたが、体の自由がきかず、声も出せない。…天上を見つめて思案している間にも、足はどんどん腫れていき、すべすべと張りつめた皮膚に蟻が這うようなむず痒さが走る。…すでに中位の冬瓜(すぶい)ほどに成長した右足は生っ白い緑色をしていて、ハブの親子が頭を並べたような指が扇形に広がっている。(『水滴』 7p)
これは戦後五十年たった頃の話なんですね。なぜ徳正の足が腫れたのか。その腫れた足から水滴が落ちるんですね。それを夜ごと傷を負った兵隊が飲みにくる。隊列を組んで。実は徳正は鉄血勤皇隊に取られていて、師範学校の生徒といいますから、当時では恵まれている人々、そこに取られていて、艦砲射撃にあって、部隊は壊滅し戦友たちが倒れていくんですね。逃げようとしたときに石嶺という同郷の友人が死にかかっている。ひとりの看護女性からパンと水を持ってきてもらって石嶺に飲ませる。ところが当人も水を飲んでないものですから、それを取り上げて全部飲んでしまうんです。その場を「許してくれ」っていって逃げて石嶺は死ぬんですけど、その記憶がずっと五十年間あるんですね。ある日突然腫上がって、水が滴り落ちる。石嶺を含み、壕の中で死んだ戦友たちが、戦友と言っても十五、六歳でしょうね、飲みにくるという話なんです。徳正自身も戦後苦労して沖仲仕とかしながら生きてきたんですけど、ある日、誰かの四十九日かなにかのふとした話に自分に水とパンを渡してくれた看護女性がその後、徳正自身は自決した兵隊の手榴弾の破片を浴びて気絶したときに米兵に介抱されるんですけど、その自分が手榴弾を浴びた同じ日にその女子学生は手榴弾で自決したということを知るんですね。それから徳正は酒びたりになって、そういう人生をずっと歩んできた人なんです。そこで資料を読みます。
石嶺が一心に徳正の足から滴り落ちる水を飲んでいる。
「イシミネよ、赦してとらせ」
「土気色だった石嶺の顔に赤みが差し、唇にも艶が戻っている。…
立ち上がった石嶺は十七歳のままだった。朱色の唇にも微笑みが浮かんでいる。ふいに怒りが湧いた。
「この五十年の哀れ、お前に分かるか」
石嶺は笑みを浮かべて徳正を見つめるだけだった。起き上がろうともがく徳正に、石嶺は小さくうなずいた。
「ありがとう。やっと渇きがとれたよ」
きれいな標準語でそう言うと、石嶺は笑みを抑えて敬礼し、深々と頭を下げた。壁に消えるまで、石嶺は二度と徳正を見ようとはしなかった。薄汚れた壁にヤモリが這ってきて虫を捉えた。明け方の村に、徳正の号泣が響いた。(『水滴』)
これは実話がもとになっているらしいんですね。座間味島というところで集団自決があった。そこでお父さんが殺鼠剤を奥さんとか子供に飲ませて、木刀で殴り殺す。でも当人は死に切れずに生き残ってしまうんですね。あるとき、足が腫れて、同じような状態になったという。それをある座談会で目取真さんが聞いて、それをもとにして書いた。目取真さんはこう言っています。
「沖縄の各地には終戦直後、戦死者たちの養分を吸収して、大きなカボチャや冬瓜ができたという話がたくさんあります。戦死者が植物を育てたり、植物に姿を変えて生き延びている」
PTSDってありますね。PTSDは脳の記憶ではないんですよね。体の記憶なんです。だからレイプというのがそうなんですね。体に刻み込まれた拭いがたい記憶なんですね。脳の記憶ならまだだませるとしても、体の記憶ってだませないですよね。集団自決して、家族は殺したけど自分は死ねなかったという、あるいは戦争中石嶺を見殺しにしたような経験が誰でもあるんですね。戦争中は誰でもそうなんです。その自分がどこで赦されていくのかという、人の罪はどこで赦されるのかというのが目取真さんの文学の、あるいは沖縄文学の、ひとつの大きなテーマだと思います。今日はここについては詳しく触れませんが、こういう経験と記憶をもった人は、いったいどうやって赦されるのか。この小説に対して「えらく赦しが簡単だ」なんて残酷な批評を浴びせたりする人もいるんです。でもね、明け方の村の徳正の号泣が響いたというところ。ここの読み方、感じ方じゃないですかね。五十年経って、吠えるように泣くしかないんです。それ以外に、言葉というものはない。それに、目取真さんはそのことを直接は言っているわけではないんですけど、死者は生き残った者を赦しているということなんだと思うんです。これはたぶん親の死を看取るときとか他人の死を看取るときに必ず後悔が残るんですよね。あのときこうすればよかった、ああすればよかったと。その先ずっと自分を苛んでいる人もいるんです。でもね、死者は赦しているんですよね。この徳正の場合も五十年かかった。このことを奥さんのウタに言おうかなと思ったけど、結局自分は言わずに「このままいわないだろうな」ともいうんですね。正直ですよね。ただ明け方、号泣した。赦されていないという精神の深い自覚が身体を異形化したのだということ。これは実はね、私は後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)という病気なんですけど、何かといったら、靭帯が骨になっていくんです。本来靭帯はそういう役割じゃないのに骨になって支えようとするんです。私を骨になってまで支えようとしたという。病気ってそういうところがあるんですよね。だから治癒というのはその魂の奥深い了解が必要なんだと。治るかどうかは別にしてです。その深い了解のところで徳正は号泣したんです。これは精神が身体をどのように異形化していくか。実は私たちの病気や癌とかもそうなんです。異形化させていく訳ですからね。
乳房の中の海
次に精神の身体化ということを純化させて最初に表現した作品が、『海の匂い白い花』という小説かなと思います。
最初はただのおできかと思っていたが、一週間もしないうちに初潮前の少女の乳房そっくりに固い張りをもって盛り上がり、きれいな形の先には幼い乳首のようなものまである。…平たく広がった左の乳房の脇に淡い桃の色をした拳くらいの盛り上がりがあり、それはほんとうに少女の乳房のようだった。…やがて三つ目の乳房の先が開き、ゆっくりと口を広げて、なかからわずかに透ける白い触手が伸びていく。ゆらゆら揺れながら広がる触手の花芯に顔をのぞかせたのは、鮮やかなオレンジ色の熱帯魚だった。白い二筋の帯とオレンジ色の体に黒い目。イソギンチャクに棲む五センチくらいのクマノミは、数百本の触手のなかで体を反転させ、花びらから離れて宙を泳ぎ、再び花の奥に潜っていく。…それから間もなくして祖母は死んだ。…祖母のことを思い出すたびに、穏やかな死に顔と白い触手の花の中で戯れていたクマノミの姿が重なる。その美しい色が私には、家族に送った祖母の最後の思いやりに思えてならない。裏の座敷には今でもわずかに海の匂いが残っている。(『海の匂い白い花』 81〜82p)
目取真さんはこういうメルヘンなところもある作家なんですね。他の生物が同居する。それから死後他の生物になるというのもあるんです。人間と他の生物との境があまりないんですね。ここも目取真さんの、あるいは沖縄文学の特徴かもしれません。だいたい生死の境目があまりないし、人間と他の生物との境目が必ずしもない。身体は他の生物を寄生させ、他の生物のように変わっていく。それは動物だけではなく、植物のようにも。そういう生類としての裾野のようなものを持っている。そういうとらえ方をしているんではないか。
これまでは身体について見ましたが、次は魂について見ていきたいと思います。
魂で見る
『目の奥の森』。目取真さんのタイトルってね、これがいったい何を意味しているのかってのが難しいんですよ。この『目の奥の森』ってのが何かというと、米兵に強姦された17歳の女の子が主人公で、その強姦されたときに砂浜で仰向けに見ていたアダンの赤い花の森のこと。強姦されたときに少女の目の奥に焼き付けられた森の光景を共有しよう、それを描こうとしていると思うんですね。どこにも説明がないんですけどね。戦後、米軍に占領された島に貝を採りにいってた女の子がいて、米兵四人に強姦されるんです。ところが村の大人たちは誰もそれに反撃しようとしない。ただひとり、盛治(せいじ)という、小夜子にほのかな恋心を持っている男の子が、米兵が再び強姦目的に島に泳いで渡るんですけど、それを見ていて、盛治はひとりで銛を持って泳いでいき、海の中で二人を突き刺すんですね。そして追われて山の洞窟に逃げて、手榴弾を一本だけ隠し持っていたんですけど、そこに米軍から催涙弾を打ち込まれて逮捕され、長いあいだ留置されたあと出てくる。強姦された小夜子はその後、村の青年にも強姦されて妊娠して、その子は里子に取られて発狂するんです。それから時が経ち、晩年になって施設に小夜子は預けられている。盛治は催涙弾を浴びたのが原因で失明しているんですね。二人は遠く離れたところにいるんです。目の見えない盛治と施設に預けられた小夜子。七十代になってそれぞれの生活が描写されます。
盛治は、天気のいい日には護岸に座って海を見つめている。(102p)
「我は今も(わにゃなまん)、お前の(いやーが)ことを思っておるよ(うむてぃうんど)…明日は雨か…我が声が(わんがくいが)、聞こえるか(ちかりんな)、小夜子…。」(『目の奥の森』120p)(小夜子は)介護施設の庭の手すりにもたれ、海の方を見ている。サトウキビ畑を渡り、丘を上ってきた風が、姉の短く刈った白い髪を乱す。姉は気持ちよさそうに目を細め、笑みを浮かべる。その横顔を見つめ、こんなに穏やかな表情を見たのはいつ以来だろうと思った。
ふと、姉の唇が動き、何か言ったようだった。
え、何?
姉は海を見つめたまま、何も答えなかった。ただ、姉がつぶやいた言葉は耳に残っていた。
かすかな風の音とともに。
「聞こえるよ(ちかりんどー)、セイジ。」(『目の奥の森』202p)
魂の声が聞こえていたんですね。こういうことって皆さんにもあるかと思います。この作品はそういうことの入口だったと思います。魂が魂の声を聞く。
霊力(セヂ)ということ
次は『帰郷』という作品です。ここでは魂が見えるのか見えないのかということがすこく大事な要素になっています。目取真さんの中でははっきりふたつに分かれている。魂の見える人と、見えない人。私たちもヤンバルの森で、その目で見られていたんだなと思うと怖いというか、そういうのもあります。で、この『帰郷』というのは、なんでこれが『帰郷』というタイトルなのかというのもあるんですけど。こういう話です。
ジョギングしている男の人がいるんですね。公園を通っていく。公園の軒の下に老人の死体が見える。当然みんな見ていると思うんだけど、どうも自分にしか見えてないということに気づくんですね。実はそこは昔の風葬場だった。亡くなった人は自分が死んだら風葬してほしいといっていて、親戚の方達が実はそこに風葬のために埋めていたけどそれは誰にも見えない。ジョギングしていた彼には見えていたんですね。そこにユタであるおばあさんが、遺体を掘り起こして洗骨している。そのおばあさんがこう言うんです。
「この骨はこの姉さんの旦那さんのものでね。ぜひ風葬にしたいって言うもんだから、あそこの軒下に寝かせてあったんだけどね。この間の台風のときはとても心配したさ。…他の人には見えないようにしてたのに、あんたはよく見えたね。はあ、あんた、とても霊力(セヂ)の高い生まれだね。」(『帰郷』137p)
セヂというんですね、霊力のことを。これは資料の一番最後のページに折口信夫の『琉球の宗教』という本から関連する箇所を引用しておきました。スヂと書かれていますね。セジとかスヂとかシヂとかいうそうです。もともとは「スヂ高い神」というふうに神の霊のことを言っていたらしいのですが、やがて守護霊のことを指すようになって、守護霊からその人の霊的な性質、霊力をスヂというようになった。次のところ、『面影と連れて』ではサーという言葉になっていますけど、そういう言い方をしている。スヂが高い人は、実は必ずしも幸せではないんですね。見えなくていいものが見えてしまう。人の本質のようなものも。『面影と連れて』の作品の中で、おばあが「うち」に何度も「人には言うなよ」という場面があるんですけど、この男、『帰郷』の當真(とうま)という男には心ひかれる女の子がいて高校生なんですね。資料読みます。
ひそかに互いが心を寄せあう高校生の神里(かんざと)にも「見えている」。
「あれが見える?」
軒下のコンクリートを指さす。…
「人の姿?」
「見える?」
「見えるよ。あそこが頭で、肩で、そこが左手でしょう。少し斜めになっている。で、ここが足かな…でも、これ、何なの?」(『帰郷』143P)
本土文学でこういうことを正面からいうとなんかインチキ臭い気がするんですけど、沖縄ではごく当たり前。実際どこを歩いても戦場ですから、あるいは海でも、死者のそういう霊が漂っているという感覚がありますよね。彼らは逃げられないから、そこにずっと生きていく訳ですから、もともとそういう精神文化のところですよね。目取真さんの一番基礎にあるカンフチ、「神の口」というのかな、そういうことが神様からおりてくるということ。そういうのがごく当たり前にあって、ノロやユタなどそういう精神文化のあるところですから、そこを素地にして、目取真さんは明らかにセジの高い人ですね。でないとこういう文章は書けないでしょうね。文学的な創作ではないです。同じテーマを扱った作家に桐山襲(きりやまかさね)という人がいます。ほとんど私と同世代の人ですが『面影と連れて』という目取真さんの作品、ひめゆりの塔で火炎瓶を投げた同じ事件を桐山襲は『聖なる夜 聖なる穴』という作品にしています。そのなかで主人公は娼婦なのですが、パッと突然いうんです。「いま炎が上がった」と。見えているんですね。桐山も魂が遠い光景を観る場面を描いています。『面影を連れて』という作品では「セジ」は「サー」ということばで出てきます。主人公は「うち」という女性なんですね。スナックに勤めていた「うち」の彼は海洋博の工事現場に潜っていたんですね。その活動家と恋仲に陥るんですけど、でも互いにからだには触れないんですね。八重山出身の活動家、「あの人」ですね。そのふたりの魂の交流を描いている。この活動家は最期自分に火をつけて死ぬ。その女性「うち」におばあがこういうんです。
「あんたは霊力(サー)の高い生まれだからね。人の見えんものの見えるさ、といってね、うちの体をあちこち触ってどこも変わってないねと確かめてから、魂(まぶい)の話を聞くのはいいけれどね、いっしょに行こう、って言われても絶対について行ってはならんよ。…それから、魂の見えることはおばあ以外の人には絶対いってはならんよ、と言われたさ」(『面影と連れて』51P)
この目取真さんの作品の中の「あの人」もそういうもの、これは死者の霊なんですけど、それが見える人として描かれています。ここで「うち」という主語はこの女性の魂のことです。私という自意識ではなく、魂が「うち」。自分の魂が自分に話している。主人公は「私」ではないんです。私の魂。これはね、日本の近代文学とは極めて大きな違いだと思います。通常近代文学では一人称の主語は「私」ですから。でもこの小説では魂である「うち」が死にかけている私に話しかける。主語は魂です。
生霊(いちまぶい)と死霊(しにまぶい)
次に『内海』という作品。ここでは生霊(いちまぶい)というものを扱っている。どういう話かというと、夫によるひどい家庭内暴力を受けて、奥さんが小学校に上がる年齢の男の子の手を引いて、母の実家に逃げるんですね。そのときに母はすでに自殺を覚悟していて、実際に死んでしまうんですけど、その逃げる途中の風景が資料にあります。最初の台詞はその男の子のものです。
「向こうからお母さんが歩いてくるよ」
サトウキビ畑に目をやる母の動きが伝わる。
「ほら、お母さんが歩いてくる」
…
「行きましょう」
その声の響きに、ああ、見えてないのだと思った。母に促されてサトウキビ畑の方に歩きながら、私は何度も振り返って遠ざかっていく水色の傘を見た。(『内海』 192P)
少年は自殺する前の母の魂の姿を見ているんですね。ここが大事なところで、目取真作品の中には魂が姿として見える場合と、そうでなく単なる光として見える場合があって、この場合はいわば、イチマブイ、生霊っていうんですかね。死ぬ前の母の霊魂の姿を見ている。魂というのは量とベクトルがあるんです。この魂がどちらに行くかというベクトルを持っている。魂はいろんな出方をするけど、ここでは姿を持っている。
先ほど触れました『魂込め』を魂の側面から改めて見ますと、こういうことになるかなと。資料を読みます。
村に伝わっている魂込めの儀式は、それほど難しいものではなかった。魂を落とした場所にそのときに着ていた衣服をもって出かけていき、御願(うがん)を捧げる。帰りに小石を三個着物に包み家に持ち帰ると、落とした人の側で御願を捧げ、着物を着せる。それで落ちていた魂は元の体に戻り、ぐったりしたりぼんやりしていた者も元気になった。(『魂込め(まぶいぐみ)』(14P)
「ウタは、その木の近くまで来て、木陰に一人の男が座っているのに気づいた。水色のTシャツを着た男の横顔を眺め、もしやと思いながら近づくと、やはり幸太郎の魂だった。…魂を目にするのは久しぶりのことで、しかもそれが幸太郎のものなので、さすがにウタも緊張した。(同上15P)
このように魂は姿を持っている。水色のTシャツを着ている。さっきのお母さんの傘も水色でした。水色って、たぶん意味やサインがあるんでしょうね。幸太郎に宿ったアーマン、ヤドカリはウタから見ればオミトという幸太郎のお母さんなんですね。戦争中食べ物がないものですから、オミトはこの浜辺で産卵したウミガメの卵を取ろうとして機銃掃射で殺されるんです。だから幸太郎は孤児なんですね。それでアーマンはお母さんの生まれ変わりかもしれないという見方をしているんですね。転生という考え方がここにはありますね。転生」という考え方は沖縄に伝統的なものなのか、あるいは目取真さんの中にある、ある傾きなのか。このアーマンを幸太郎の体から引きずり出して、スコップで殴り殺すんです。
以前この会(レゾナンスCafe)を私の家でやったときのテーマは「石牟礼道子とヒルデガルト」でしたが、石牟礼道子さんの時には「魂込め(たましごめ)」というんですね。水俣でもそういう儀式をしているんですね。東京からいろんな人が水俣の総合科学調査のために来るんです。それで石牟礼さんが「魂込め」をするというのがある。だから沖縄だけではないんですね。沖縄の又吉栄喜という芥川賞作家に『豚の報い』という小説があって、そこにも魂込めが出てきます。魂の感覚がそうなんだなぁと思いますが、キリスト教とはちょっと違う。だから必ずしも目取真さんだけではないんですね。私が注目している沖縄の論客の親川志奈子さんがこう言ってるんです。仲井眞知事が政府から東京に呼ばれたことがありましたね。そのときね、「確かに仲井眞知事に裏切られて頭に来ているけど、ウチナーンチュは彼が無理矢理東京に拉致されて魂を落として帰って来たと感じている」という。こういう使い方を日常でしているんですね。仲井眞さんは魂を取られたんだと。マブイ落ちしたんだと、あの顔はね、だからかわいそうだと。そういうこともあるんだ、面白いなと思います。私たちが魂という言葉を使うときはちょっと何かスピリチュアルというか、何か浮遊するものを感じますけど、そうじゃないんですね。現実です。
次にもう一回『面影と連れて』に戻りますけど、強姦されたあと「うち」は裸同然の姿でウタキの森に導かれるようにしてよろよろと歩いていくんですね。そこで「あの人」がガジュマルの木に首を吊って下がっている姿を見るんですね。そして家に帰り着いて、「うち」のからだから離れた魂がうちのからだに語りかけます。
「うちはまだ息していた。ゆっくりと小さく胸が動いていた。細く短い息の音が聞こえよった。今なら間に合うから早く戻りよ、って言ったおばあの言葉を思い出したけどね、うちは迷ってね、自分に聞いたさ。あんた、戻りたいね、って。うちは答えたさ。もういいよ、って。これ以上哀れしなくていいよ、って。あの人のところに行こう、おばあのいる所に行こう、って。そうだね、その方がいいよ、って、うちは思った。だからね、うちは戻らんかった、自分の体にね、戻らんで、倒れてる自分の胸の動きがゆっくり止まってね、体の中の何もかもが止まって、薄く開いた目の光が消えていくのを見守ったさ。ああ、終わったんだね、これで終わったんだ、そう思うと同時に急に寒くなってね。…うちは思い出したさ。夕暮れ時にね、心寂(ちむしから)さぬや、っておばあが言っていたのをね。そうだね、おばあ、ちむしからさぬ…。うちは最後にそうつぶやいたさ。」(74P)
そういう距離感を持っている。これは折口信夫も書いていますけど、魂は肉体と不離不即であるが、自由に離脱する。だから生と死の距離も私たちが思うほど遠くないというんですかね。ここが大事ですね。死を恐れない距離感を持っている。自分の魂が自分自身と対話するというのはなかなか分かりにくいかもしれません。だがキリスト教には異言(いげん)というものがあります。異言というのは、自分自身の中の霊が勝手に語るんです。それで自分自身は意味がわからないんですが、自分が自分を言い当てていくんですね。自分の魂が自分のことを言い当てているんです。新訳聖書の中にはごく普通に出てくるんです。教会ができた頃は異言で祈ってたんです。自分では何を言っているのか分からない。それを解釈する人がいて、お前はいまこう祈っているよということを、これも聖霊から与えられるんですね。沖縄にはいまもそういうのが残っているんですね。いま教会で異言で祈ったら異端視されます。
赦し
私が一番好きなのは、この『群蝶の木』という作品です。映画化できるなら映画化したいと思うくらいに。これは魂の姿、あるいは死後の魂について非常に具体的に言っているんです。これはどういうストーリーかというと、徴兵に対して自分の腕を自分で焼いて徴兵を忌避した昭正(しょうせい)という男と、従軍慰安婦として狩り出されたゴゼイという女の悲恋ですね。群蝶の木というのは、ユウナというムクゲのような黄色い花が咲く木があって、それが蝶のように見える。そのユウナの木の下で娼婦であるゴゼイと昭正はつかの間の時間を盗んでそこで逢い引きするんですね。その思い出の場所だったんですね。しかし米軍が侵攻してきたときに山奥の壕に逃れるんですけど、そこで昭正は日本の兵隊からスパイの嫌疑をかけられて殺されるんですね。壕から昭正が引き出されるときに昭正がじっとゴゼイのことを見る。でもゴゼイは何もすることができない。昭正を殺した日本兵に、その直後抱かれる。見殺しにしたという、そういう罪の意識がゴゼイの中に強くあるんです。ある日、すでに気が触れているゴゼイがほとんど裸同然の姿で村祭りに闖入してこう言うんですね。
「ショーセー、助(たしき)けてぃとらせ、兵隊(ひーたい)の我連れ(わんそう)てぃ行くしが。」(『群蝶の木』212p)
「昭正、早(へー)く隠れ(かくり)よ、ヤマトゥの(ぬ)兵隊(ひーたい)がお前(いやー)捜しに来よるが。」(同上228p)
こうやって自分のことを責めているんですね。最後のところ、その昭正がゴゼイにこう言うんです。
「ゴゼイ、ゴゼイよ。何を悔いる必要のあるか。物思(むぬうむ)ゆる体も、最後はユウナの木のそばの川のように、ねっとりと濁って混じり、この世のものすべて海で一つになるさ。てのひらから滴り、髪から滲みだし、太ももを伝い、目や耳から流れ、弛んだ細胞の一つ一つから珊瑚の産卵のように宙に舞っていくもの。その最後の塊が木のうろのような口から出てゆくと、蝶の形となって室内をゆっくり飛び、閉じた窓のガラスを抜けて、月明かりに舞っていく。」(同上257p)
こういう終わり方をしている。気がついたことですが、「ゴゼイ、ゴゼイよ。何を悔いる必要のあるか。物思(むぬうむ)ゆる体も、最後はユウナの木のそばの川のように、ねっとりと濁って混じり、この世のものすべて海で一つになるさ。」ここまでは昭正の一人称。次からは人称が変わってますよね。作者目取真さんの目でしょう、「てのひらから滴り、… 蝶の形となって室内をゆっくり飛び、閉じた窓のガラスを抜けて、月明かりに舞っていく」という言い方をしている。この死後の姿のとらえ方は沖縄・琉球のとらえ方なのかどうかということはちょっと私にはわかりませんね。これは仏教の影響なんだと思うんです。これは「大河の一滴、空の微塵に散れ」という仏教的な感覚ですよね。琉球の信仰の中にこういうとらえ方がもともとあるのかどうかはわかりませんが、目取真さんの中にはこういう一瞬の余地もあるということなのかなという気もしています。ここでもうひとつ、理解していただきたいのは、この昭正が殺されるのをゴゼイは見殺しにした訳ですから、それを戦後五十年とか六十年ずっと責め続けていて発狂してしまう訳です。それに対して昭正は赦している訳ですよね。何を悔いる必要があるかと。その魂は蝶の形になって出て来る。目取真さんの話の中で蝶はよく出てきます。それは実話に即しているらしく、祖母のお母さんという方だったかが亡くなったときに、枕元を数羽の蝶が飛んでいったという光景の、直接の記憶かどうかはわかりませんが、そういう記憶をもとにしているということなんです。さきほどのおばあさんの乳房にクマノミが泳いでいるとか、蝶に変わるという、いわば精神が身体化していくというそれも慰めである。この蝶も慰めでしょうね。死者から生者に送られる慰めであるというとらえ方をしている。ここでも赦しということが大きなテーマになっている。
しにまぶい
一番最後に死霊(しにまぶい)ということに触れて終わりたいと思います。『内海』では母が自殺する、睡眠薬を大量に飲んで死ぬんです。その時のかすかな記憶が子供にあるんですね。それでおじいさんの家に引き取られていて、そのある日、おじいさんが「火の玉を見に行くか」といってぶらっと森の頂上に連れて行くんです。これはそのときの光景です。語り手はこの少年です。
祖母はもう寝たのだろうか。それとも、今夜も機を織っているのだろうか。見つけ出した家の明かりを眺めながら、ぼんやり考えていると、屋根の上に何か小さな火が浮いているのが見える。胸が高鳴り、目を凝らすと、オレンジ色の丸い光の玉は屋根の上を平行にゆっくりと移動し、庭に降りて石垣の門から出ていく。しばらく副木の屋敷森の間を見え隠れしていた火は垂直に浮かび上がると、もう一度家の屋根の上で静止し、短い尾を引いて内海に浮かぶ島の影に消えていった。
「見ゆたんな?」
うなずいただけで返事はできなかった。いつの間にか、涙が首筋まで伝わっていた。「あの海でな、いつも見守っておるんよ」…(211p)
この部落(しま)で生まれたものはよ。死ねばみなあの海を渡って島に行く。そしてずっと見守っているのさ」(『内海』212p)
これも目取真さんの死後の魂の了解のしかたなんだなあと。先ほどの場合は姿を持っていましたけど、ここでは姿を持っていない。光になっている。沖縄の信仰では死んだら神になるんですね。祖霊神、自分の先祖の霊が神ですから、死んだら神になるという。昔は六日とか七日でなっていたらしいです。最近では三十年くらいかかるという。これは折口信夫が書いているんですけどね。そういうことがあるんですが、先祖はみんな神になって子孫を守る。それがウタキである訳ですね。そういうとらえ方をしている。資料にある柳田国男が書いた死後の世界ですが、こうなっています。
沖縄諸島では、あの世をグショウ(後生)と呼んでいるが、それをことのほか近いところのように考えているようである。
沖縄の民俗学者仲松秀弥は『神と村』でこう書いています。
この世と彼の世との間に、魂の往来が可能と想定してこそ、はじめて素朴な古代沖縄人は、祖先を神とし、これを腰当(けあて)としてまつるようにしたのである。(『神と村』)
このように見れば目取真さんの文学はとりわけ特別ということではなくて、だから死ねるというのがあるんだと思うんですね。死者と生者の距離が非常に近い。この作品の場合は、光になる。マブイというのと、ヤマトのタマシイというのは違うということも、折口信夫の『琉球の宗教』なかで触れられていますので、あとの資料に目を通しておいてください。。
全生類への裾野という存在の全体性
最後にまとめていう訳でもないですけど、先日沖縄県知事選がありましたよね。選挙の実況中継を見てたんですけどね、当選が決まったときの玉城デニーさんの様子が私にとってはすごく印象的で、当確が出た瞬間にずっとこう天を仰いでいたんですね。ああいう光景は珍しい。翁長さんの霊と話をしていたんだと思うんですけど、かなり長い時間そうしていた。そのあと何をしたかというと、いきなりカチャーシーを踊り始めた。見事。もともと踊りとか謡(うた)というものはこういうものなんだろうなと。踊りの専門家でもなんでもないのに、一流の踊り手なんですね。一人の政治家がね。死者の霊と非常に近い、それから謡や踊りが専門として分化するのでなくてひとつの存在の全体の中に息づいている。それは目取真さんが芥川賞作家でありながらカヌーを漕ぐというのとまったく同じだと思うんです。沖縄の魂はある種の全体性を持っている。それだから『虹の鳥』の中のマユのことを――そこで魂とは言ってないけど、マユの命のことが魂なんですね。だから全体性というのは、「私」という近代的個人ではなく、「命」の全体性として主語が成立しているという、ここがものすごく大事なことなんだろうと思うんです。だからデニーさんの存在全体がパッと命の全体性として輝くように出てくる。その主体は生者と死者の間を行き来する魂でもある。つまり生と死は区別されてなくて、その肉体は、あるときはスブイ(冬瓜)となり、あるときはクマノミとともに棲み、全生類に開かれた生命の主体としてその人の命がある。そういう捕まえ方をしているんだろうと思うんです。そこはやっぱり決定的な違いではないかなあと思っています。
だから別の言い方をすれば、なぜいま私が沖縄に注目するかというと、日本の近代はどこかで間違ったんだと思うんです。ほとんどくるっていますよね。こうなっているのは。どこで間違ったのかということをいま本当に深刻に考えなければならない。そのときにいま沖縄の人たちがもつあのしなやかさと強さ、本当に緊張したときでもパッと誰かが謡いだして踊りだすんですね。あんなことは私の中にはないんです。それはね、たとえば戦争中に、米軍から追われて墓に逃げ込むんですね。沖縄の墓は大きいですから。孫たちを連れて入ったとき、米軍の戦車がずらっと並んで銃口を向けるんです。そのときおばあさんがどうしたかというと、ダーッと墓の外に飛び出して突然ね、唐船ドーイ(とうしんどうい)という一番テンポの速い唄を踊りだすんですね。それで結局助かるんです。そういう精神文化を持っている。主体の成り立ちがやっぱり違うんじゃないか。私たち日本人は、文学史の中の、夏目漱石とか芥川とかの系譜の中に自分を見ているけれども、自分の脳を自分だと思っているけど、本当の人間の生の姿というのは、やっぱり違うんじゃないか。沖縄の人たちにとってみれば生死の境目をずっと歩んで来たから、本当の人間の姿を知っているんですよね。非常に苦しいだろうけど、原初的な命というものを主語として知っているからこそ、外的な力としての暴力には走らない。徹底的な平和主義―非暴力直接行動で抵抗し続けているんだと思います。
目取真さんのこれまでの作品の主人公――抵抗する主人公は、みんな「小さくて弱いもの」ですが、みんな一人単独の抵抗ですよね。でも今、辺野古では、海の上でも岡の上でも、目取真さんは孤立した個人ではないですよね。現実として、ともにパドルを漕ぐ仲間がおり、座り込みを続ける仲間がいる。だから今後目取真さんが『希望』という名の絶望を超えてなにかを書かれるとすれば、それはやはり個人ではなく「共同の力」。それに触れていかれるのではないか。現場での、一人ではなく多くの人びとの、ともにある苦悩と悲しみと喜びをその体で知っておられる目取真さんが、共同の力に――それは人間という枠を超えて生類全体の力にみなぎった、決して潰えることのない「希望」というものがあるとすればそれはどのようなものか。そのことを書かれるのではないか。そういう期待があります。でもそうなるかどうかは、実は私たちにかかっているんだと思うんです。
「 わんがくいが ちかりんな(我が声が聞こえるか)」と南風が聞いています。
「 ちかりんどー(聞こえるよ)」と答えたい。
重いテーマでしたが、これで私の話は終わります。
※1 鉄血勤皇隊 wikipediaより
鉄血勤皇隊(てっけつきんのうたい)は、太平洋戦争末期の沖縄県において、防衛召集により動員された日本軍史上初の14~16歳の学徒による少年兵部隊である。
沖縄戦において正規部隊に併合され、実際に戦闘に参加し多くの戦死者を出した。
臼田夜半(うすだ よはん) プロフィール
1946年、福岡県北九州市門司区生まれ。
ヒルデガルト研究会主宰
著書には随筆集『病という神秘』(教友社)、翻訳書『聖ヒルデガルトの病因と治療』(ポット出版)、『ネロの木靴』(地湧社)がある。
最新刊『聖ヒルデガルトの病因と治療を読む』(ポット出版)が2018年12月23日発売予定。

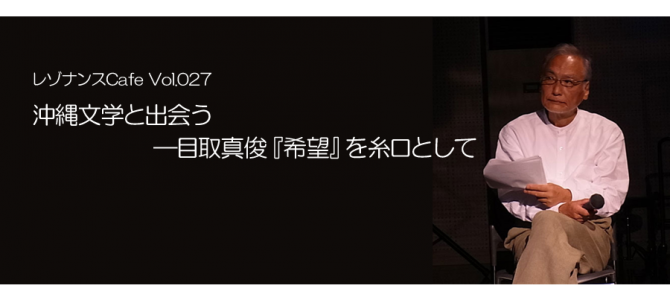
Pingback: レゾナンスCafe Vol.038「臼田夜半さんを偲ぶ会」 – RESONANCE cafe